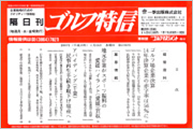2025.07.05
2025/7/5 ゴルフ場業界にもキャンセル徴収が広まる動き
一般社団法人・日本ゴルフ場経営者協会(NGK)は今年1月に【ゴルフ場のキャンセル料に関する実態調査】を実施したが、一般社団法人・静岡県ゴルフ場協会でも「キャンセル料に関する調査」を今年1月に実施し、3月に調査結果をまとめたことがわかった。
県内ゴルフ場を対象に実施したもので、キャンセル料徴収を実施しているのは、同協会に加盟していないゴルフ場14コースを含め82コースの集計で半分強の53・7%にあたる44コースで、非加盟の14コースはホームページ等で調査し集計したとしている。キャンセル規定があるコースのうち、3コースが実質的に運用していないとの回答だった。
また、徴収していないと答えたゴルフ場(38コースが回答)の状況としては、「具体的な検討あり」が9コースでうち6コースが年内開始予定、それ以外が9コース。徴収しているコースと年内の6コースを加えると、今年中に50コース(61・0%)が整備される計算だ。
徴収しているコースの地区割合は西部支部地区65・0%、伊豆支部地区56・5%、東部支部地区50・0%、中部支部地区42・9%となり、やや西部地区が高い。
実はゴルフ場の協会が相次いで実態調査を行っているのは、PGMやアコーディア・ゴルフなどチェーンゴルフ場が相次いでキャンセルポリシーの見直しを行い、キャンセル料徴収に踏み切っている影響もある。
PGMによると、キャンセルポリシーは同グループのコースほとんどにあるが、常時徴収していたのは10コース程と少なく、有名無実化していた。それがコロナ禍でゴルフの人気が高まり、雨天時の直前キャンセルも増えたことで見直したところ、ホテルで使っていたキャンセル料請求回収自動化のシステム(Payn)が請求作業をほぼ自動化できると知って、昨年10月からまずビジターを対象に、今年1月からは会員を対象に本格運用を開始した。そして実績を上げ、キャンセル回収率も高く、入場者数でも好調を維持していることを先のPaynのインタビューで公表していた。
実はゴルフ場にも昔からキャンセルを徴収する規約はあったが、市場環境の変化で、キャンセル料を徴収することが少なくなっていた。関東はキャンセル料を徴収しなくなったところが多いが、中部・関西のゴルフ場にはまだキャンセル料を徴収する文化は残っていたという。
ちなみに、PGMと同じ平和グループ傘下となった㈱アコーディア・ゴルフは約3カ月前の昨年12月22日に、今年4月1日からキャンセルポリシーを改定することを表明していた。あるコースの例ではキャンセル料は土・日祝日がプレー日を含む7日前から1組あたり(例として8000円)、平日が3日前より(例5000円)。キャンセル料の対象は予約代表者および同伴者の判断、都合による組単位のキャンセル(天候不順、体調不良等)。キャンセル予約を1カ月以内で振替プレーの場合は、キャンセル料免除する。ただし、以下の場合は請求の免除対象として、〝・天災、天候、その他やむを得ない事情によりゴルフ場がクローズする場合、・以下期間の平日におけるキャンセル料は土日祝扱い(GWやお盆期間の平日暦、年末年始の平日暦)〟。・請求方法は予約代表者に対しSMS等を通じて請求。・WEB予約経由のキャンセル処理は、キャンセル料規定に同意したものとみなし、SMSもしくは予約代表者の登録住所に請求書を送付。・補足 ・キャンセル料は、理由の如何を問わず一切返金いたしません〟等としていた。
PGMの例のように、直前キャンセルや無断キャンセルの抑止などマナー向上が図れれば、キャンセルされた枠の販売も可能でキャンセル料の徴収(ちなみにキャンセル料は消費税等が課税されない)で収益を増やすことも可能。請求作業に困難が伴うことから、これまで積極的でなかったが請求化自動ツールが出てきたことで、ゴルフ場業界にもキャンセル徴収が広まる動きとなっている。
ちなみに消費者庁が実施した、「キャンセル料に関する消費者の意識調査」(2024年1月)によると、キャンセルした商品・サービスの上位は「ホテル・旅館等の宿泊」30・6%、「航空機」15・2%、「ツアー旅行」12・5%の順で、「スポーツ施設(ゴルフ場など)の利用契約」は2・2%の9番目。キャンセル規定の業界標準が浸透しているのは会社数が少ない航空業界だが、やはり初見の方の利用も多い宿泊業界はキャンセル料徴収ではゴルフ場業界よりも先に進んでいると言われている。