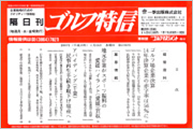2025.09.05
2025/9/5 日本ゴルフ場支配人会連合会、24年度幹事会総会開催
日本ゴルフ場支配人会連合会は、5月29日に千葉県柏市内のホテルにて東西の支配人が会合し、2024年度幹事会総会を開催した。
まず労働安全衛生委員会から2024年度の労災事故は合計957件で20年前などより減少したが、死亡災害が6件発生するなど減らない現状に懸念の声が挙がった。また過去20年間の死亡災害の傾向は機械操作や伐採作業関連の事故で8割を占め、人員不足や従業員の高齢化が要因としている。これを受け、シートベルトの確実な着用と樹木伐採に関するチェックシートの使用徹底を求める緊急通達を全国のゴルフ場へ発出することが承認された。シートベルト非着用者を作業から外す措置や、メーカーへの警告音システム導入の提案もなされた(24年の労災事故件数関係の詳細データは次号で紹介)。
環境管理委員会では、生物多様性への取り組み(サーティバイサーティ)、プラスチックごみ削減に向けたアンケート調査、水質調査結果の確認などが報告された。西日本では、過去2年間の猛暑により約70%近くのゴルフ場でグリーンにダメージが生じ、24年はさらに悪化した。従業員や来場者への夏場の暑さ対策も喫緊の課題となっている。また、西日本で深刻化するマツ枯れは、70%のコースで年間21本以上、半数のゴルフ場で年間10本以上発生しており、コースの安全性への影響が懸念されている。
総務税務委員会では、カスタマーハラスメント(カスハラ)がフロント、レストラン、キャディなど様々な場面で発生している現状が報告された。特にカスハラ事例が多い関西圏では基本方針が作成され、ポスター掲示などで対策が進められている。
人手不足も深刻で、早朝勤務や屋外作業といった労働環境が採用の障壁となっている。賃上げも検討されているが、入場者数の限界から抜本的な解決には繋がりにくい状況としている。そのため、省人化運営の構築やスキマバイトの活用などの情報共有が提案された。西日本ではキャンセル料徴収に関した講習を行い、大手では年間約72万人ものキャンセルが発生し、徴収代行業者を活用して、他にも広がりつつある。代行業者の利用(成果報酬制)により従業員の負担なく徴収できる効果が報告されたが、状況報告はカルテルとの関係もあり取り扱いには注意が必要とした。
その他、暑さ対策としてのWBGT計測機活用、南海トラフ地震注意情報時の危機管理、ゴルフ業界を挙げた災害協定による地域貢献、将来的なデジタル化を見据えたマイナンバーカードの入場時活用等も検討との報告があった。
ゴルフ活性化委員会では、新規ゴルファー創出活動として、WAGスクールやWomen’s Golf Dayへの参加募集が実施され、ゴルフ経験のない方やリタイア層を対象とした企画、従業員向けスクールなども行われた。加盟ゴルフ場へのアンケート調査を通じて、ジュニア育成や女性ゴルフ振興などの各県の活性化策に関する情報収集、「2025年問題」(団塊の世代のリタイア等での人口減少)に対する取り組みや対策についても情報交換が行われた。
インバウンドに関しては、西日本で空港に近いゴルフ場を中心に韓国、中国、台湾からの受け入れが進む一方で、マナー問題(ゴミ捨て、ロッカールームでの行動など)やトラブルが課題として挙げられた。積極的な受け入れを行うコースがある一方、受け入れに消極的なコースも存在しているという。インバウンド効果により、九州地区では従業員数が2年連続で増加したと報告している。
また西日本では、関西ゴルフ連盟の来場者から協力金(1人50円)を集めたゴルフ振興事業が注目された。他の地区では同様の協力金徴収や地区連盟と支配人会が連携した活動は難しいという意見も出たが、担当委員からは試行錯誤の上で現在に至ったと説明している。
財政面では、25年度の収支計画でJGAからの補助金が廃止されるため、今後の運営方針が課題となった。
総会後の常任幹事会で、20年ぶりに西日本から選出された藤本賢治新会長(くまもと中央CC総支配人)は、「現場の実動部隊の集合体として、東西が力を合わせ業界発展に尽力したい」と抱負を述べた。2期会長を務めた東日本ゴルフ場支配人会連合会の八木秀夫会長(立科GC)は副会長に就任した。
なお、総会後の懇親会には自民党ゴルフ振興議員連盟の赤池誠章事務局長(参議院議員)が駆けつけ、地方創生やゴルフ振興を目的にスポーツ庁等の補助金活用も提案していると案内して、協力を求めた。